今年の関東地方は昨日(六月十日)に梅雨入りしたそうだ。雨が続くと途端に家中が湿っぽくなって床がベタベタする。換気しても良くならないのでとうとう今朝からエアコンを稼働して除湿をしている。

庭なしの、しがない集合住宅住まいなので晴れた日に畑を耕すわけにも盆栽いじりもできないので猫の額ほどのベランダでプランター菜園で食料の自給に努めるている。この時期になると油虫が繁殖して葉物野菜は大打撃を受けるのが例年の年中行事で頭が痛い。殺虫剤を使ってしまえば食べる気がしなくなるのでただ見守るだけだ。
傘を刺さずに済む日はできるだけそこら辺を散歩して体力・脚力の強化に努めているが、雨の日は日がな一日音楽鑑賞と読書で過ごすしかない。晴歩雨読の日々、それにも飽きると台所で包丁を握り気分転換の調理実習に明け暮れている。
便利な世の中でインターネットで検索すればほとんど全ての料理レシピや手順が調べられる(今日は大根の皮のきんぴらを作った)。若い頃には考えられない時代になった。これからは人工知能が家庭にも進出して、星新一のSF小説のように機械に向かって喋るとその声色を判断して自動で食べたい料理が出て来るようになるのも夢ではないかもしれない。とはいうものの、それでは退屈な時間の解消にはならないだろうから、暇人の趣味として手作り料理は家庭でできる貴重な生き甲斐として残るに違いない。
生きることは食べること、食べられることは生きている証拠である。そして問題は、何を食べるかだろう。最後は食欲、「残るは食欲」。
図書館の蔵書検索機能を活用して食に関する著書を調べてみたら、檀一雄や邱永漢、阿川佐和子の面白そうなエッセイがヒットした。さっそく取り寄せて読んでいる。小説家の蘊蓄や、恐るべし。文筆家の阿川家親子の食事を題材としたにエッセイも味が濃い。この梅雨は食に関する読書で鬱陶しい季節を乗り切りたい。
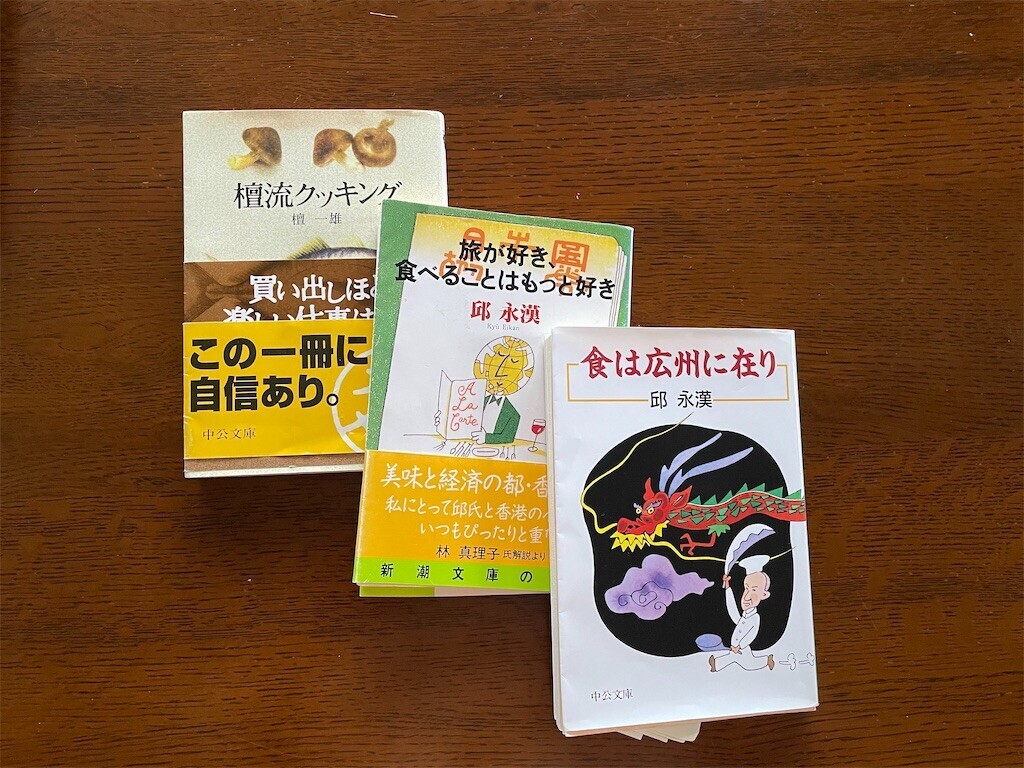
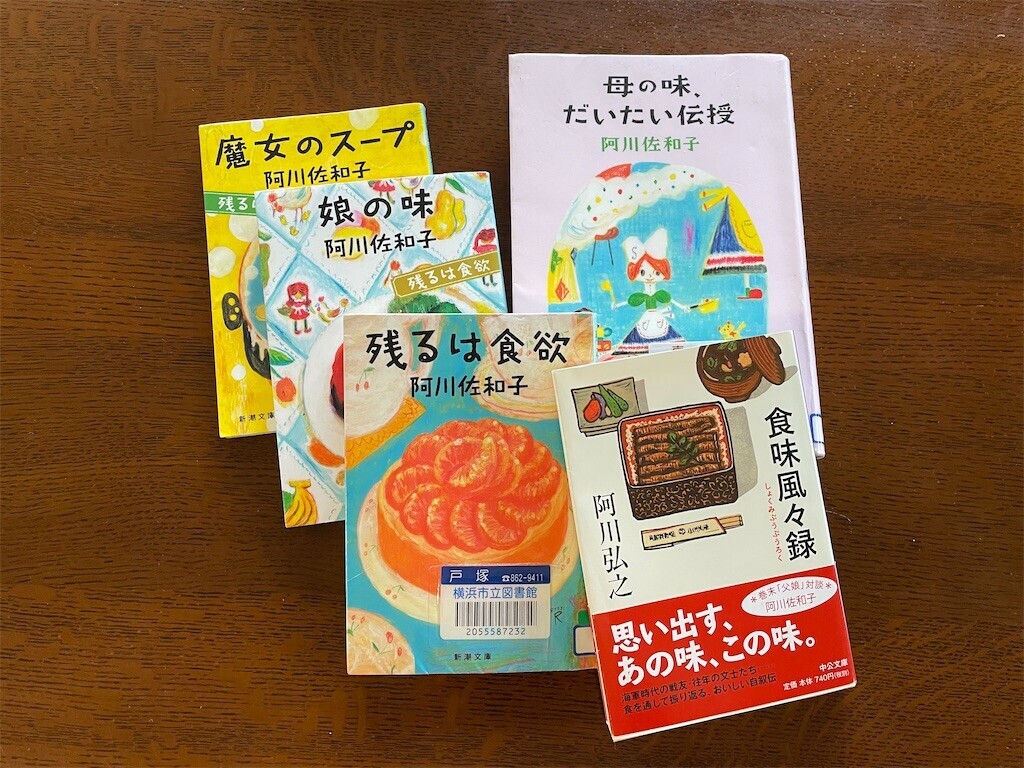
物心ついて70年余り、これまでいろいろな美味、珍味、妙味を口にしてきたけれど、これらの本を読むとこの世には如何にたくさんの知らない食べ物・料理があることかとあらためて驚かされる。まだまだ食べたいものがたくさんあるので落ち落ち病気にもなれないぞ。